ふるさとテレワーク

hometown

総務省が平成27年度に実施した「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」において、NTTコミュニケーションズ株式会社が大船渡市などとコンソーシアムを組んだ「都市部企業のニアショア開発センターと自営型ノマドワーカー(移住者)の地域交流による多様な分野・世代が学び・働ける『大船渡市・地域人材育成拠点』整備事業」(以下「ふるさとテレワーク地域実証事業」という。)が採択先となりました。この事業では「大船渡ふるさとテレワークセンター」(「ふるさとテレワーク地域実証事業」終了後に名称を変更。以下「大船渡テレワークセンター」という。)を構築し、都市部企業やフリーランスなどのIT技術者がテレワークを実践する実証を行いました。
今回は、コンソーシアム構成員として事業に参加した株式会社地域活性化総合研究所の福山宏氏に、参加のきっかけやこれまでの成果、今後の構想についてお話を伺いました(掲載内容は取材当時平成29年1月中旬時点のもの)。
福山氏は東日本大震災直後から大船渡市に移住し、防災情報などを伝達する研究等を行い、平成24年8月には、「防災メディア」 と 「市民メディア」 の融合への取組を目的に立ち上げた「NPO法人 防災・市民メディア推進協議会」の設立メンバーとなりました。また、平成26年9月からは株式会社地域活性化総合研究所に所属し、大船渡市の人口減少問題に取り組んでいます。
福山さんは「NPO法人 防災・市民メディア推進協議会」のメンバーとして、平成26年、高校生や保護者向けにアンケートを実施されたそうですね。
平成27年度にふるさとテレワーク地域実証事業に参加したきっかけを教えてください。
ふるさとテレワーク地域実証事業はどのように進められたのでしょうか?

▲大船渡テレワークセンター内の様子
最初はふるさとテレワークの取組がうまく稼働しなかった部分もあったようですね。軌道に乗り始めたのは何がきっかけでしょう
「大船渡テレワークセンター」にはサテライトオフィスだけでなく、コワーキングスペースを併設されましたが、最初は地元の人が使ってくれなかったそうですね。
すぐに仕事を斡旋できるわけではないので育成から開始されたわけですね。

▲大船渡テレワークセンター内のコワーキングスペースで実施されたセミナーの様子
働きたくてもフルタイムで働くことのできない女性の仕事を生むことにつながっていますね。

▲コワーキングスペースを活用して仕事をする女性
加えて、お母さんがパソコンで仕事をしている姿を見ている子どもたちは、働くことに対する認識やイメージも変わってきますね。

▲子連れでコワーキングスペースを訪れる女性も
ふるさとテレワーク地域実証事業が大船渡で行われたことで、地元の方や企業などがどういった面で変化したか教えてください。
プラットホームができたことによる広がりは大きなものになっているようですね。

▲コワーキングスペースでのクリスマス会の様子
最後に、大船渡テレワークセンターを活用した今後の展開について教えてください。
ありがとうございました。

お問い合わせ
テレワーク相談センター
0120-861009
9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
お問い合わせフォーム
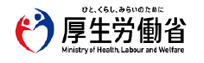












平成25年当時、大船渡市とNPO法人 防災・市民メディア推進協議会では、大船渡市の人口減少の大きな要因は、高校卒業時に約9割の若者が市外に進学や就職で転出してしまうことであると考えていました。
そこで、ICTを活用した遠隔学習環境や遠隔就労環境を整えてはどうかという仮説を立て、事業化検討のために平成25年度復興庁の企業連携プロジェクト支援事業に応募し、「ICTを活用した遠隔ビジネス大学校とオフィスの開設事業」が採択されました。その事業化検討の一環で実際の高校生や保護者のニーズを把握しようということになり、平成26年1月に大船渡市、陸前高田市、住田町の高校1年生から2年生の生徒と保護者の全数アンケート調査を実施しました。
このアンケートの中でなりたいと思っているキャリアに対する質問があり、「地元で学べて遠隔でも働ける環境があれば(地元に)残りたいですか?」と尋ねたところ、72%の高校生が「それがあるなら残りたい」と回答し、保護者は80%が「残したい」と答えたのです。それまで「地元から出ていくつもりですか?」という質問に約85%の高校生が「出ていく」と回答し、90%の保護者が「出したい」と答えていたにも関わらずです。
正直なところ、もっと田舎が嫌で都会に出ていく人が多いのかと思っていたんですね。ところがそういった人は2割程度で、大学・専門学校などの「学べる場」と自分が希望する「働きたい仕事」があれば、約8割が「地元に残りたい」と思っていました。しかし、現実には学べる場がないため、学びたいと思ったら大船渡を出ていくしかない。また、働くとしても職種が限られているので結果として大船渡を出ていくという選択肢しかない状況にありました。
環境整備ができれば、残ってもいい、残りたいと意識が変化することが分かり、遠隔で学べる環境作りの検討を開始しました。これが「スマートキャリアカレッジ構想」です。