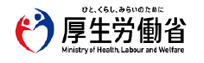非IT企業ながら、テレワークを活用し積極的な重度障がい者雇用を行っているほか、特別支援学校とも連携し、障がいがある学生との交流を通してテレワークを浸透させる取り組みを継続的に行っている。また、オンラインで感謝の気持ちを伝え合うサンクスカードの導入や、イベントを通し孤立を解消する取り組みを行っている。
会社概要
組織名:名称:株式会社スタッフサービス・クラウドワーク
創立:2020年 ( (株)スタッフサービス・ビジネスサポートより在宅事業を継承)
組織代表者:役職:代表取締役社長
氏名:曽根 徹哉(そね てつや)
業種:サービス業 (スタッフサービスグループの事務処理サービスおよび付帯する支援業務)
所在地:神奈川県
総従業員数:正社員:26人 定年再雇用:4人 派遣社員:5人契約社員:400人(全員在宅就労の重度身体障がい者) (2022年10月時点)
テレワークの導入形態:終日在宅勤務
テレワークの利用者数(過去1年間):435人(2022年9月時点)
テレワークの導入
テレワーク導入の目的(経緯)
テレワークによる重度身体障がい者の就労推進を目的とし、スタッフサービスグループの事務処理および営業支援のためのデータ作成入力、検索・調査系業務を在宅で行っている。
テレワーク導入による成果(目的の達成)
身体的な特性や地方の交通機関のバリアフリー化の未整備、雇用機会の不足により働きたくても働けない重度身体障がい者に、テレワークによる完全在宅就労での雇用機会を提供することで、2016年から2022年の6年間で2府30県に400人の雇用を創出することができた。2022年9月に実施したアンケートの中で「あなたの現在の生活と仕事のバランスはとれていますか?」の問いに対し、400人の在宅社員のうち85.8%が「とれている」と回答があったことから、多くの社員のワーク・ライフ・バランスを実現できている。また、高い定着率を実現しており、入社1年後の定着率は97.0%となっている。
基本的な事項
制度の整備状況
重度身体障がい者を全員在宅就労の形態で雇用しているため、テレワークを前提とした就業規則を整備している。就業規則は社内ポータルサイトに公開し、社員が随時確認できるようにしている。入社時に就業規則の説明会を実施している。重度身体障がい者にとって、自宅は最も安心安全な環境であり、通勤がないことにより身体の負担が少ないため、テレワークは重度身体障がい者が能力を発揮して働ける環境であると考える。
実施環境の整備(労務管理面)【労働時間管理】
労働時間の把握方法としては、社内ネットワークへのログイン時間およびログアウト時間のログを取得しており、無届の残業や休日勤務有無のチェックと、後述する1日3回の定時ミーティングでの進捗確認における業務量調整により、在宅社員の働き過ぎを防止している。また、出退勤時刻の入力やシフトの管理ができるオンラインツールを導入している。
【中抜けの取り扱い】
就業規則に条項を定め運用している。中抜けの予定が分かっている場合は、事前に所属長に届け承認を受けることにしている。ただし、緊急の用件がある場合で、所属長の承認が受けられない場合は、電話で代理者にその旨を告げ、職場を離れることができる。就業時間の管理は、オンラインツール上で入力された時刻により判断している。
【テレワークを行う際の作業環境整備】
面接時に自宅を訪問し、生活動線や作業部屋について、セキュリティの確保(家族の出入りがない個室か)、部屋の広さ、照明の明るさ、窓の有無、椅子(ひじ掛け確認)、エアコンの有無、PCを置く机の広さ、部屋とトイレなどの動線に危険個所がないかなどのチェックを、本人や家族の同意のうえ、実施している。入社以降は、毎月労働安全衛生委員会にて無作為に選出した20名の在宅社員にアンケートを配布し、作業環境のセルフチェックを実施している。回答率は100%で、その結果について社内ポータルサイト上で全従業員に周知すると共に労働安全衛生委員から全社員に職場の安全についての注意喚起などを行ってているため、業務上の事故は発生していない。
【テレワークを行う際の費用負担の取り決め】
自宅の光熱費、電話代、事務用品代などのうち業務負担分として、毎月3千円を「在宅勤務手当」として支給している。会社とのネットワーク接続で、自宅のインターネット環境を利用する場合は、「通信環境調整手当」として2千円を支給している。
【メンタルヘルス対策を含む健康確保対策】
健康管理室を設置し、保健師・精神保健福祉士がオンライン健康相談を実施している。利用状況は月間で平均8~10件程度。相談窓口があることで、気軽に専門家に相談できる安心感を持ってもらえたり、健康に不安を持つ在宅社員を把握し、主治医の受診を促したりするなどのフォローが可能となっている。
実施環境の整備(情報通信環境面)【在宅勤務】
通信環境については、全社員にPC本体、モニター、キーボード、マウス、Webカメラ、ヘッドセットを貸与している。モバイル通信カード以外は原則一律で貸与している。要望があればトラックボールマウスを貸与したり、自分でヘッドセットを装着できない社員にはマイクとスピーカーを貸与したりするなど、障がい特性に応じた対応をしている。
また、ネットワーク接続については、モバイル通信カードを貸与するか、自宅のインターネット環境を利用しVPNで接続することとしている。
ワーク・ライフ・バランスに関する事項
健康で豊かな生活のための時間の確保【労働時間の柔軟な取り扱い】
9:00~19:00の間で1日6時間の勤務時間を設定し週30時間就業としている。在宅社員は、その範囲内で生活介助の時間・定期通院の時間・体調管理のための休憩時間などを確保しながら就労できるように各自が勤務時間を決めている(画像1 例①)。稀なケースではあるが画像1 例②のように通院の関係で6時間の勤務時間に満たない勤務シフトのパターンも認めており、その差分は他の日に就労し週30時間勤務になるよう調整をしている。その他、健康管理上の事由に限り月2回までのシフト変更も認めている。2022年8月時点で192種類の
勤務シフトを運用しているが、これにより入社前の自分の生活スタイルを維持しながら就業できることが高い定着率 (画像1 シフト設定のイメージ)につながっている。
【長時間労働対策、時間外・休日労働時間の削減】
時間外・休日の就業は原則禁止としているが、やむを得ない理由がある場合は所属長への事前の届出が必要となっている。それだけでなく、1日3回の定時ミーティングで個々の業務の進捗を確認しており、業務量を調整することで残業を未然に抑制しているほか、PC操作ログを記録しており、PCの利用時間の監査を毎月1回実施している。在宅社員は2021年度実績で法定外労働時間並びに、無届の時間外労働および休日労働はゼロとなっている。
【健康の確保に向けた取り組み】
労働安全衛生委員会に在宅社員も委員として参加しており、安全衛生に関して、予め会社で決めた安全衛生に関するテーマを労働安全衛生委員が在宅社員に展開し、意見やアイデアを集め、労働安全衛生委員会で発表後、議事録と共に社内ポータルサイトで共有している。また、在宅社員からの申し出があった場合は、保健師とのオンライン面談も実施している。
【休暇取得促進の取り組み】
法定年次有給休暇の取得促進を呼びかけ、取得状況のモニタリングを実施している。有給休暇の取得率は2020年度79.3%、2021年度82.9%と向上している。
多様な働き方の選択
【育児・介護の要のある者】
原則9:00~19:00の間で1日6時間の勤務時間を設定し週30時間就業のルールの範囲で育児や介護の必要がある在宅社員についても育児や介護の時間を考慮し、就業時間を設定している。
【高齢者・障がい者】
在宅社員は全員重度身体障がい者を採用している。在宅社員の雇用形態は契約社員である。2021年度は65人採用した。 2022年度10月時点において、就労者数400人が完全在宅就労している。2022年度は103人を採用予定。
【女性活躍に関わる取り組み】
全在宅社員400人のうち、134人(33%)の女性社員が在籍している。ダイバーシティ推進の一環として、スタッフサービスグループの特例子会社との共同企画で「障がいと向き合いながら育児と仕事」をテーマに障がいがある女性社員4人で座談会を行い、在宅社員も参加した。社内ポータルサイトにレポートを掲載して情報共有している。
【障がいがある未就労者や学生に向けた取り組み】
テレワークを働き方の選択肢の一つとして浸透させるために、地方のハローワークや障がい者支援機関に呼びかけ、未就労者を対象としたテレワークでの「お仕事体験会」を開催している。特別支援学校とも協力し、障がいがある学生と在宅社員との交流会も開催している。2021年7月~2022年8月に、毎月1回以上、計16回開催した。障がい者87名が参加し、15名が就労に踏み切った。
社員の満足度
2022年9月実施した社内アンケートでは、「職場の雰囲気は良いですか?」という設問に対し、在宅社員の86.4%が「良い」と回答し、「スタッフサービス・クラウドワークは好きですか?」という設問に対し、在宅社員の88.3%が「好き」と回答している。
他社の模範となる取り組みに関する事項
労務管理上の工夫
【テレワーク作業環境の工夫】
テレワークの課題である孤独感を解消するために、オンライン上に職場のコミュニティ(チーム)を形成している。インターネットを使った検索による調査やデータ入力などの業務をチーム単位で対応することで、在宅社員同士で連携しながら業務を遂行している。在宅社員の中から適任者を選出し、各チームをサポートするリーダー役を任命している。 1日3回の定時ミーティング(10:00~10:45、13:30~14:30、15:00~15:30に各20分ずつ実施)では、チーム力を発揮するための土台として必ず雑談することとしている。労働安全衛生委員会への参加、イベントの企画実施、社内報制作などの施策にも在宅社員が参画
でき、チームの枠組みを超えた「 横のつながり」を持てるよう工夫している。
【人事評価の工夫】
半期ごとに活躍した在宅社員を表彰する制度がある。半期に一度、業務上のスキルチェックシートを活用した個別面談を実施し、目標確認と振り返りを実施している。
【人材育成(社内教育・研修)の工夫】
入社後1カ月目は会社の基本的なルールに加え、オンライン上でチームの一員として連携しながら仕事をするためのコミュニケーション、情報の取り扱いなどの研修を行っている。2カ月目は先輩社員と合流し、業務研修を通じ仲間と連携しながら働くことを実践的に学んでいる。在宅社員を管理する社員も、オンライン上のコミュニケーションスキルを高めるための研修を実施している。
【ハラスメント対策への取り組み】
「職場のハラスメント防止規程」を制定し、入社時にハラスメント研修を実施している。また、全社的に年1回アンケートを実施している。さらに、就労相談ダイヤルを設置し、専任のサポート担当が相談を受け付けている。
【コミュニケーション活性化の工夫】
オンライン上で感謝の気持ちを贈り合えるサンクスカードを導入している。「必要とされている」「役に立てる」「感謝される」ことが実感でき、チームワークの向上につながっている。 “感謝の気持ちを贈り合う日”を設けたり、年始に“今年の抱負”を贈るイベントを開催したりして活発なやり取りを促している。さらに、管理スタッフが社内SNSで積極的に事務所の出来事を発信し、在宅社員はリアクションやコメントをするなど双方向のコミュニケーションを実現している。 (画像6 サンクスカード)
事例検索へ戻る事例検索へ戻る