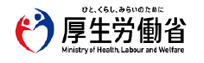外国籍の従業員も母国でのワーケーションを行うときは、現地時間での就労を可能にするなど、海外からも柔軟なテレワークができるように整備している。また、海外クライアントが増加し時差のある国との対応を求められるようになったが、会議が長時間や深夜にならないよう、スケジュールの管理を工夫している。
会社概
組織名:
名称:シェイプウィン株式会社
組織代表者
役職:代表取締役
氏名:神村 優介(かみむら ゆうすけ)
業種:情報通信業(PR支援事業,WEBプロモーション企画・WEB制作事業,マーケティングコンサルティング事業)
所在地:東京都
総従業員数:正社員:7人 パート:2人(2022年8月時点)
テレワークの導入形態:終日在宅勤務 部分在宅勤務
モバイル勤務
ワーケーション
テレワークの利用者数(過去1年間):9人(2022年8月時点)
テレワーク導入の目的(経緯)
テレワークの導入
経営理念「チャレンジする人が尊敬される社会を創る」の実現のため、社員が結婚・出産・病気・介護といったライフステージの変化に直面しても働くことを諦めず、チャレンジし続けられるよう、働く場所や時間の制約なしに多様な働き方ができるテレワークを2020年から本格的に導入した。社内コミュニケーションのオンライン化、ペーパーレス化、クラウドサービスの活用などにより、出社しなくとも問題なく働ける環境の整備を進めた。全社員がテレワークのみならずスーパーフレックスタイム制、短時間勤務、ワーケーションなどの制度を利用可能としたことで、地方や海外在住者の採用も可能になった。
制度を整えれば終わりというわけではなく、お互いを尊敬し合う社内文化を創ることも重要であると考え、上司・仲間とのフラットな関係性の構築、コミュニケーションを深めお互いを知り違いを認め合うこと、感謝を伝え合うこと、チームワークを大切にすることなどを行動指針として示し、誰もが安心して発言や行動ができる環境作りと社内文化の醸成にも取り組んでいる。
テレワーク導入による成果(目的の達成)
テレワークの導入と共に、フルタイムでの勤務が難しい子育て中の短時間正社員の要望でスーパーフレックスタイム制を導入した。また、外国籍社員の要望によるワーケーションの導入などを制度に反映していった結果、社員の離職率は2019年度の80%から2021年度には25%まで低下した。全社員がテレワークとスーパーフレックスタイムを基本とし、フルリモートも可能という働き方が企業イメージの向上につながり、求人応募数が2019年度と2021年度を比較すると4倍に増加した。
顧客との商談においては、Web会議やチャット・メールの活用、クラウド上でのデータ共有などを進め、オンライン上で国内遠方企業や海外企業への営業活動を推進した。コロナ禍でも海外企業の日本市場への注目度が高かったことも功を奏し、海外クライアントからの国内PR案件の受注が増加した。
基本的な事項
制度の整備状況
テレワーク勤務規定を整備している。オンラインではカバーしきれないコミュニケーションを補うために、週1回の原則出社日を定めているが、距離や家庭の事情などに応じて出社するかしないかは自由とし、4名がフルリモート、5名が出社とテレワークのハイブリッド勤務をしている。
実施環境の整備(労務管理面)【労働時間管理】
始業・就業時間と中抜け時間をPCやスマートフォンから入力できるクラウド型の勤怠管理システムを導入している。モバイルワークやワーケーションの場合もGPS機能で位置情報が記録されるため、客観的な労務管理ができている。業務の進捗やスケジュールをチームで共有するため、勤怠打刻と合わせて、出勤時に社内の勤怠報告チャットで勤務開始の連絡と、当日の勤務場所(出社・モバイルワーク・ワーケーションなど)、業務内容などを報告することとしている。
【中抜けの取り扱い】
子育て中や治療と仕事の両立をしている社員のため、家庭の予定や通院などの場合、休憩時間として中抜けを許可している。出勤報告時に不在の時間を伝え、中抜け中は休憩開始・終了時間を勤怠管理システムに入力することで勤務時間を管理している。
【テレワークを行う際の費用負担の取り決め】
文具などの消耗品や書類の印刷代、書類などの発送費などは全額会社で負担している。通勤手当は定期代支給から出社時の通勤費の実費精算へと変更した。在宅勤務中の通信費や光熱費などを補助する目的で「テレワーク手当」を1カ月当たり1万円支給している。
【メンタルヘルス対策を含む健康確保対策】
テレワークがメインでも孤独にならないよう、雑談用チャットの活用を推奨すると共に、月1回オンラインランチ会を開催している。入社後3カ月は会社やメンバーとの信頼関係を構築し、業務に慣れてもらうためのタスクを与えると共に、担当チームごとの週1回の定例打ち合せとは別に、マネジャーと週1回の1on1ミーティングを行うことで、疑問点や不安をすぐ解決できる機会を設けている。また、入社3カ月経過の社員はメンバーのチームとのコミニュケーションストレスの度合いを把握するために、相談しやすい場作りと客観的な判断ができるように担当マネジャーを変えた形で3カ月ごとの1on1ミーティングを実施している。
■ 実施環境の整備(情報通信環境面)
【在宅勤務】
サブモニター・キーボード・PCスタンド・ブルーライトカットシートなどを、本人の要望に応じて会社から支給している。
【モバイル勤務】
テザリング可能なスマートフォンを会社から支給している。外勤時などの空き時間や、自宅だと勤務に集中できないときなどは、シェアオフィスやWi-Fi環境の整った場所での勤務を可能としている。
ワーク・ライフ・バランスに関する事項
健康で豊かな生活のための時間の確保【労働時間の柔軟な取り扱い】
パートタイムを含む全社員にスーパーフレックスタイム制を適用している。始業終業時間の自由な設定と私用による複数回の中抜けを可能とし、働く時間を体調や家庭の事情などに合わせ柔軟に選択できる。出社日は、通勤電車の混雑を避け午前は在宅勤務し、午後からの出社など自由な働き方を推奨している。
【長時間労働対策、時間外・休日労働時間の削減】
時間外や休日の勤務を避けるため、勤務時間外はチャットやメールの返信は不要とし、経営陣から注意喚起している。海外クライアントの増加により、時差のある対応が必要な場合でも、社内共有のオンライン上のカレンダーで勤務時間をスケジュール共有し、会議が長時間や深夜にならないよう、打ち合せ可能な時間を管理している。
【健康の確保】
テレワーク中の姿勢や椅子、照明などの作業環境が健康に与える影響や、好ましい姿勢、作業環境について社内勉強会を開催した。
【休暇取得促進の取り組み】
テレワークとスーパーフレックスタイム制が定着した結果、家庭の事情や通院などによる休暇取得の必要がなくなり、有給休暇の取得が低調になったが、取得率が低い社員への個別アプローチや、テレワークと休暇を組み合わせたワーケーションの推奨により2021年度の取得率23%から2022年(10月現在)取得率41%にアップした。ワーケーションに関しては、沖縄などの旅先に長期滞在してテレワーク、子供の夏休みなどの長期休暇は遠方の実家からテレワーク、2名在籍している外国籍の社員は母国への帰国時に海外に数カ月滞在してテレワークするなど、制度の活用が増えている。
海外でのテレワークで日本との時差が大きい場合は、現地時間での勤務を可能としている。例えば、カナダに帰国中の社員の場合は、日本と12時間ほどの時差があり日本時間に合わせた勤務だと昼夜逆転してしまうので、カナダ時間で勤務をし、国内での勤務と同様にタイムカードで出退勤を申請し、労働時間を管理している。また、ワーケーション先で展示会やカンファレンスに参加するなど、人脈作りと現地の最新トレンド収集も可能になった。
多様な働き方の選択
【育児・介護の要のある者】
テレワークとスーパーフレックスタイム制の活用により、夕方に子供の送迎や育児時間のために業務を中抜けし、夜に業務に戻るなど柔軟な働き方が可能になった。また、突然の子供の病気や保育園、学校の休校・休園時でも仕事を休まず子供の側で働くことができるようになった。
パートタイムから短時間正社員への転換や、短時間正社員でも管理部門の責任者を務めたり、社内売り上げトップのクライアントをメイン担当するな
ど、家族との時間を大切にしながら責任ある仕事に意欲的に取り組み、家庭とキャリアの両立を実現する女性社員が1名から3名に増加した。
【非正規雇用社員】
テレワーク利用において正規と非正規雇用の間で待遇の差はない。パートタイム2名、社員2名は遠方に居住しており、出社なしのフルリモートで勤務している。
社員の満足度
2022年2月に実施した社内アンケートで、「会社が実施している、ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みや姿勢への総合的評価を教えてください」という質問に対し、全社員が「大変良い」と回答をした。
他社の模範となる取り組みに関する事項
推進体制
【経営トップのコミットメント】
テレワークをはじめとする自社の働き方の取り組みを、社長自ら会社説明動画で紹介している。テレワーク導入後、社長が海外移住して率先してテレワークを実践すると共に、育児のための中抜けも活用している。
【社内周知の工夫点】
2021年以降、応募、面接から入社までをすべてオンラインで行うフルリモート勤務者が入社したため、社内のマニュアルや研修動画などを整備し、入社初日からリモートでも社内環境に順応できるような環境を整えた。
環境整備
【テレワーク導入時の業務の見直しや点検】
管理部門はテレワーク導入にあたり、出社不要で対応できるよう、入社書類などの社内重要書類は押印不要とし、契約書締結はクラウドサービスを導入した。電話代行サービスの利用やオンライン請求書発行システムの導入も行った。クライアント支援部門は全員が同時進行で複数案件を担当しており、属人的なスケジュール管理だと抜け、漏れ (画像5 業務棚卸シートのイメージ)などの恐れがあったが、どこからでもアクセスできる
タスク・プロジェクト管理ツールを導入したことで、タスク漏れの解消とスピード感のあるやりとりが可能になった。現在も職種ごとに業務の棚卸しを継続的に行っている。
労務管理上の工夫
【作業環境整備の工夫】
チャットなどのテキスト中心のコミュニケーションを補うため、15分程度の短いオンラインミーティングや電話などの手段を組み合わせたコミュニケーションを促している。社内の会議室には大型モニターを設置し、出社している社員とテレワーク中の社員がリアルに近いコミュニケーションの取れる環境を整備している。
【人事評価の工夫】
勤務時間の長さで評価するのではなく、個人の成長にフォーカスした人事評価のため、出社でもテレワークでも評価に差が出ることはない。頻繁にコミュニケーションが行われており、テレワークでも業務の進捗や勤務態度などをマネジャーが把握しやすい。
【人材育成(社内教育・研修)の工夫】
勤務時間の長さで評価するのではなく、個人の成長にフォーカスした人事評価のため、出社でもテレワークでも評価に差が出ることはない。頻繁にコミュニケーションが行われており、テレワークでも業務の進捗や勤務態度などをマネジャーが把握しやすい。
フルリモート入社の社員の場合、入社時に不明な点があっても、出社する社員に比べて聞きづらい状況になることがある。入社直後は不安が大きくなる時期と捉え、入社3日以内にオンライン上で社員全員と会う「自己紹介ツアー」「歓迎ランチ会」などの取り組みを行っている。会社全体で歓迎の意思表示をすることで、気軽に相談しやすい雰囲気を早期に構築できるよう工夫している。
事例検索へ戻る事例検索へ戻る