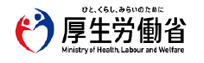非IT企業ながら、中期経営戦略でダイバーシティや生産性向上に向けての取り組みの一つとして、テレワークの促進を行うことを示し、煩雑なプロセスを全て排除するような改革やサテライトオフィスの設置など、あらゆる業務・意識改革を積極的に行いテレワークの制度・仕組みを定着させている。また、テレワークを活用して地方支社勤務の女性従業員を東京本社など都市部の業務を遂行させる「リモート・キャリア」などによる女性活躍への取り組みも優れているものと評価された。
会社概要
組織名:アフラック生命保険株式会社
創立:1974年
組織代表者:代表取締役社長 古出 眞敏(こいで まさとし)
業種:融業、保険業
所在地:東京都
総従業員数:5,090人(2022年3月時点)
正社員:4,535人 契約社員:555人 参考:派遣社員 約1,800人)
テレワークの導入形態:日在宅勤務 部分在宅勤務
モバイル勤務 サテライトオフィス勤務
テレワークの利用者数(過去1年間):4,791人(2022年3月時点)
正社員:4,292人 契約社員:499人
テレワークの導入
テレワーク導入の目的(経緯)
2015年から社員一人一人が仕事の進め方を見直すと共に、「時間」と「場所」に捉われない働き方の実現に向けた制度・インフラの整備を通して社員のワーク・ライフ・マネジメントを支援し、組織としてのパフォーマンスを最大化させることを目的とした「アフラックWork SMART*」を推進する中でテレワーク促進を行ってきた。
2024年をゴールとした中期経営戦略(2022~2024年)の5つの戦略の第一の柱に「多様な人財の力を引き出す人財マネジメント戦略」を据え、全役職員が新たな価値の創造に取り組むイノベーション企業文化の醸成を含めた組織力・人財力の向上を実現するため、ダイバーシティと「アフラック Work SMART」の推進をさらに加速させ、人財エンゲージメントを向上させている。
*社員一人一人が仕事の進め方を見直すと共に、「時間」と「場所」に捉われない働き方の
実現に向けた制度・インフラの整備を通じて、社員のワークライフマネジメントを支援し、組織としてのパフォーマンスを最大化させることを目指す取り組み
テレワーク導入による成果(目的の達成)
コロナ禍の感染症対策と経済活動の両立が求められる中でも、テレワークを活用し、お客さま本位の業務運営を確保することを実現した。また、その後もリアルな接点を活用し組織成果を最大化するために、出社とテレワークのハイブリッドな勤務体制で最適な働き方を模
索するなか、18カ月連続(2020年4月~2021年12月)で全社員の在宅勤務実施率50%以上を維持し、「場所」に捉われない働き方を実現した。常態化していた法定外労働時間が2021年は4.5時間まで削減(2016年比で72.4%減)され、有給休暇取得率は80%を超えている。 (画像1 在宅勤務平均実施率の推移)
基本的な事項
制度の整備状況
育児や介護などの理由の如何を問わず、社員だけでなく、派遣社員や当社オフィスで勤務する業務委託先社員にもテレワークを認め、「在宅勤務業務ガイドブック」を公開し、テレワークを行う際の基本的な基準などを周知している。
また、感染症対策と組織成果を最大化する業務運営を両立させるための働き方のプリンシプルとして、出社することで得られる価値を理解し、リアルな接点を活用して組織成果を最大化することを定めた「ウィズコロナの働き方のプリンシプル」を策定している。当社では機動的な業務運営を実現するため、ルールベースの思考ではなくコアバリュー(基本的価値観)に基づき、プリンシプルベースで判断することを全役職員に求めており、全社的な出社のルールは設けず、各部門がプリンシプルベースで判断し、出社とテレワークのハイブリッドな勤務体制を実現している。
さらに、時間当たりの付加価値向上/アウトプットの最大化を実現するため、2022年から全社員にパルスチェックを導入している。2週間に1回、自身・チームの仕事の仕方、時間の使い方などに関する質問をシステムで繰り返し配信し、社員は「十分実践できている」~「全く実践できていない」の5段階で回答する。所属長は、所属員のスコア平均および推移をダッシュボードで確認し、チームの働き方の改善を継続的に実施している。
実施環境の整備(労務管理面)【労働時間管理】
テレワーク実施時に所属長が所属員の状況を直接把握できない場合においても、適切に労働時間の管理ができるよう、PCログオン・ログオフ時刻が勤怠管理システムに記録・表示される仕組みを構築している。社員が申請する勤怠実績(始業/終業)とPCログオン・オフ時刻に一定の乖離(60分以上の差など)がある場合はアラートが表示され、乖離理由の記載を必須としている。
【中抜けの取り扱い】
「時間」に捉われない働き方を実現するため、適正な勤怠管理のもと、特に制限を設けず中抜けを認めており、柔軟に利用されている。中抜けが適正に利用されるように、労働時間の定義などを解説し、中抜け時間は労働時間に含めない旨を「労働時間の適切な管理に関するガイドライン」に定め、全社員に公開・周知している。中抜け時間は勤怠管理システムに登録可能で、所属長が内容を確認、承認している。
【テレワークを行う際の作業環境整備と費用負担の取り決め】
「場所」に捉われない働き方を実現するため、積極的にテレワークを実施する環境を整備することを支援している。支援の内容は以下の通り。
・ 在宅勤務環境整備手当:必要な備品などの購入補助を目的に一時金2万円を支給
・ 在宅勤務環境維持手当:テレワーク時に発生する水道光熱費や通信費を補助する目的で毎月5千円を支給(当月にテレワークを1回以上実施した社員が対象)
【メンタルヘルス対策を含む健康確保対策】
メンタルヘルスを未然に防ぐため、仕事のストレスや心身の不調、テレワークなどによる業務上のコミュニケーションの悩みに関する相談を気軽に行うための窓口を設置し周知している。また、過重労働による健康リスクを回避するため、法定に加え、自社独自の基準(連続労働時間やインターバル)を設け、仕事のストレスや心身の不調をアンケートで確認し、ハイリスクに該当する社員には産業医面談を実施している。
実施環境の整備(情報通信環境面)【在宅勤務】
シンクライアント方式のノートPC、USBシンクライアント(自宅のPCに挿入すると社内サーバーに接続される)やタブレット端末、スマートフォンを社員や派遣社員、当社オフィスで勤務する業務委託先社員にも配布している。
【サテライトオフィス勤務】
全国9カ所(新宿区、調布市、千代田区、横浜市、八王子市、町田市、千葉市、さいたま市、大阪市)にサテライトオフィスを設置し、複合機やデュアルディスプレイなど、自席と同様の環境を整備している。社内のイントラネット上で座席を予約することで簡易に利用でき、取引先訪問や他部署との打ち合わせ前後に活用することで、時間を有効活用できる。
【モバイル勤務】
モバイルツール(タブレット端末、スマートフォン)を貸与し、メールやマニュアルの確認だけでなく、Web会議への参加や報告書作成なども、場所を選ばずに社内と同様に業務遂行が可能となっている。
ワーク・ライフ・バランスに関する事項
健康で豊かな生活のための時間の確保【労働時間の柔軟な取り扱い】
「時間」に捉われない働き方を実現するため、所属長の承認のもと、全社員がシフト勤務・フレックスタイム制度(全部署でコアタイムなし)を活用し、柔軟な勤務ができる環境を整備している。労働時間の柔軟な取り扱いについては以下の通り。
・ シフト勤務は、朝7時~夜9時の時間帯で8パターンの勤務帯を1日単位で選択可能
・ 有給休暇を時間単位で取得可能(最大5日/年)
【長時間労働対策、時間外・休日労働時間の削減】
各部門が主体的に所定外労働時間と有給休暇取得率のKPI(重要業績評価指標)を設定し、実績をダッシュボードで可視化することで、所属長はWeb上でタイムリーに把握できる。
また、仕事の進め方の基本指針として「Work SMART5原則」を定め、時間外労働の削減に留まらず仕事の進め方を抜本的に見直し、生
産性の向上を図っている。年1回実施する社員満
足度を測る「エンゲージメントサーベイ」における、Work SMARTの実践に関する質問の肯定回答60%以上をKPIと定めると共に、仕事の進め方の見直しの各部の取り組み事例を社内イントラネットで周知している。
具体的な取り組み事例は以下の通り。
・ 業務効率化のための課題を検出し、部門選抜メンバーで課題解決に向けた対策実行プランを策定するプロジェクトを複数立ち上げ、課題を解決
・ 業務プロセスの自動化ツール(Power Automate)を活用し、定例メールの発信を自動化するなどして作業時間を短縮
これらの取り組みにより、2016年全社の法定外労働時間1カ月当たり平均16.3時間が、
2021年には1カ月当たり平均4.5時間と72.4%削減され、有給休暇取得率は、2021年実績で86.7%となる。有給休暇取得日数平均は、2015年13日から2021年17日と4日増加した。
【健康の確保】
「生きる」を創るリーディングカンパニーを目指すためには、社員がいきいきと活躍することが不可欠であるという考えのもと、2016年12月に「アフラック健康経営宣言」を制定し、健康経営に取り組んできた。2022年3月には、2万社以上の企業の健康ビッグデータを分析し、社員の健康上の課題や強化領域を特定し、経済産業省の「健康投資管理会計ガイドライン」に基づく“戦略マップ”を定め、「健康経営2024」として、より戦略的な取り組みへと発展させている。
①セルフヘルスチェック
生活習慣改善のため運動、メンタルヘルス(セルフケア)、食事、飲酒、禁煙の5つの
テーマを中心に、生活習慣の振り返りのための「セルフヘルスチェック」を3月に実施した。
②まいにち健康チャレンジ
セルフヘルスチェックの結果をもとに、個人目標を設定し、100日間の継続にチャレンジする「まいにち健康チャレンジ」を実施し、社員の約50%が参加。当該施策に対する社員満足度を測る実施後のアンケートでは、参加社員の
(画像7 2022年まいにち健康チャレンジ アンケート結果)
約90%が「満足・やや満足」と回答、また、約80%が「仕事や生活に好影響があった」と回答。
また、コロナ禍でのテレワークの長期化による運動不足への懸念から、昼休憩時間に任意に参加可能なオンライン運動プログラム「ちょこっとエクササイズ」を実施し、オフィスでも参加できる身体を動かすプログラムをWeb会議でライブ配信した。
多様な働き方の選択
【育児・介護の要のある者】
「短時間勤務制度」は子供が小学校を卒業するまで利用可能となっている。しかし、「時間」と「場所」に捉われない働き方を推進し、短時間勤務からフルタイム勤務へのシフトを推奨した結果、時短社員比率は2015年53.4%から2021年24.9%と年々減少し、社員のキャリア形成支援の一助となっている。
【高齢者・障がい者】
高齢者や障がい者に限らず、全社員がテレワークできる環境を整備している。60歳以上社員の91.2%(159名のうち145名)が在宅勤務実施の実績があり、1カ月当たりの平均では13.7日実施している。(2021年4月~2022年3月実績)
【契約社員など】
非正規雇用社員(有期雇用労働者)や派遣社員に限らず、全社員がテレワークできる環境を整備している。非正規雇用社員の95.9%(315名のうち302名)が在宅勤務を実施しており、1カ月当たりの平均では12.3日実施している。(2021年4月~2022年3月実績)
【女性活躍に関わる取り組み】
東京や大阪など都市部にある部署の業務を、地方に住む社員が転居することなくリモートで行う「リモート・キャリア」制度を2018年から導入し、転勤を前提としない地方社員(対象の多くが女性)のキャリアの選択肢が広がっている。現在、全国で25名の社員がこの制度によりテレワークを活用し、離れた場所で業務を実施している(本制度利用者の累計は29名)。
社員満足度
新型コロナウイルス感染症問題への対応について、2020年7月から現在まで計6回の意識調査を社員に対して実施している。直近の結果(2022年9月)では、「当社の持続可能な在宅勤務のための環境整備について」という設問に、社員の90.4%が肯定的に回答しており、2020年7月以降、全ての回で肯定回答は80.0%以上となり、社員満足度が高い状況を維持している。
他社の模範となる取り組みに関する事項
推進体制
【経営トップのコミットメント】
コロナ禍の感染症対策と経済活動の両立が求められる中で、当社は「必要業務の継続を最優先とする業種(エッセンシャルワーク)」の生命保険業として、テレワークが長期化する状況下でも、出社時と同じ水準で業務を継続するために、代表取締役社長を含めた経営陣で、全社共通の働き方に関する課題(コミュニケーション不足・深夜勤務の増加・非効率な会議の増加など)の解決についてディスカッションし、課題解決に取り組んでいる。
【社内周知の工夫点】
全社員対象のeラーニングで、テレワークやフレックスタイム制度を軸とした「場所」と「時間」に捉われない働き方を推進する意義を伝えている。また、「ダイバーシティ&Work SMART」ポータルサイトを社内イントラネット上に作成・公開し、テレワーク勤務時の部内でのコミュニケーションルールの工夫や、飲食をしながら気軽に対話を行うWeb会議システムでの交流会(「アフラックもぐもぐタイム」)の実施などテレワークの活用事例を周知している。
環境整備
【テレワーク導入時の業務の見直しや点検】
全社ペーパーレス計画を推進し、2021年までに3,759種類の帳票の廃止・電子化を行った。業界初のオンラインによる保険相談や、契約完結システムによる新たな営業体制の展開、コールセンター業務の在宅化など業務変革を実現している。
労務管理上の工夫【人事評価の工夫】
テレワークの環境下でも、所属長が適切な評価できるように、全所属長向けに「1on1トレーニング」を実施し、従来から実施する1on1を強化している。日常的な1on1に加え、全社で期間を定めて実施する四半期毎の1on1(クォータリー・1on1)の実施率は100%となっている。
【人材育成(社内教育・研修)の工夫】
「Work SMART」の意義の正しい理解推進のために全社員向けにeラーニングを配信している。また、新入社員の入社時研修にテレワーク実践のプログラム(コミュニケーションの取り方や機器操作など)を導入している。所属長には、テレワークでも適切なマネジメントができるように、オンライン特有の所属員とのコミュニケーションの工夫などについて「テレワークマネジメント研修」*をeラーニングで配信している(アーカイブでいつでも受講可能)。
*「テレワークマネジメント研修」の具体的な内容は以下の通り。
・ 情報やプロセスをオープンにし、心理的安全性を高めるコミュニケーションの取り方や上司のサポート(ラインケア)のポイント
・ 仕事と家庭の切り替え方の工夫
・ カメラは基本的に起動するなど、Web会議を成功させる工夫
【ハラスメント対策への取り組み】
「ハラスメント防止のためのハンドブック」を全社公開し、社員だけでなく派遣社員も利用可能なハラスメント・ホットライン(ハラスメント相談窓口)を社内外に設置している。また、所属長には、ハラスメント対策を含めた労務管理研修を実施し、オンラインでの所属員とのコミュニケーションの留意点として、メールやチャットに偏重することを避け、電話やWeb会議で会話の頻度を増やすことや、対面での体調管理の機会を創出することを周知している。
事例検索へ戻る事例検索へ戻る