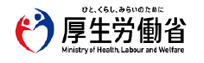生産性と多様性、どちらか一方しか選べない?
秋の季節も一瞬で終わり暦の上でも冬に突入し朝晩の温度差が激しくなってきましたが、皆さん風邪など引いていませんか。インフルエンザも流行しているのでご自愛ください。
テレワーク相談センター相談員の川田です。
今回は、「生産性と多様性、どちらか一方しか選べない?」についてお話したいと思います。
就活をしている学生が企業を選ぶ際に重要視しているのは、テレワーク勤務が、可能かどうかが大きなファクターとなっており、既に企業で働いている従業員の確保(転職防止)にも、テレワーク実施が重要と考えられています。
企業の従業員に何故テレワークをしたいのですかとお聴きすると、「自分らしく働きたいからテレワークをしている(したい)」とよく言われます。ここでいう自分らしくとは、「自分の大切なものを大切にしたい」「そのための時間が必要だからテレワーク」ということだと思います。自分のライフスタイル・ライフステージによって働き方を見直すことは自然なことで、通勤時間を減らし地理的制約を解消できる「テレワーク」は、自分らしく働きたい人にとって、うってつけの働き方です。
これまで職場には、十人十色の価値観があるにもかかわらず、生産性を効率的に上げるために、同じように考え行動できる人材を育てることが好まれてきました。均一性を高め画一的な手法を用いることが、無駄が生じず効率が良いと考えられてきたからです。
しかしながら今はVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代。企業も個人も均一的で画一的な働き方では立ち行かなくなっています。自分らしく働くことは、単なる個人のわがままではなく、自分の個性が認められ、安心して働けることであり、エンゲージメントを高めることができます。テレワークやフレックスタイム制等の柔軟な働きかたは、働く人のライフスタイルに合わせて効率的に働けるようになり、結果として全体の生産性向上につながり仕事に反映させることができる、イノベーションを生み出す強力な原動力となります。
ダイバーシティに対応する為に企業は、従来の雇用制度等を維持したまま、多様な人材の採用だけを増やしている可能性があります。この場合、企業の業績は、かえってマイナスとなる可能性があることが分かっています(*1)。つまり、企業が多様性によるプラス効果を享受するためには、ポジティブな要因を引き出していくための何らかの取組や変革が必要だと考えられています。特に柔軟な働き方については、様々な背景の人材に有意義なものとなっており働き方を変えることは多様性全般に対して非常に有用な制度であると考えることができます(*2)。
(*1) 令和元年度年次経済財政報告第3節労働市場の多様化が経済に与える影響 1 多様な人材の活躍は生産性等を向上させるか
(*2) 令和元年度年次経済財政報告第2節働き方の多様化に向けて求められる変革 1 多様な人材を活かすために必要な取組
テレワークは単に働く場所をオフィスから自宅やサテライトオフィスに変えるだけでなく、自立・自律が求められ、対応力を養う必要があります。企業が働く人の多様性を活かすために、テレワークを通し人材の自立・自律を促すことができる、多様性と生産性を両立するためにとても相性が良い制度だと考えています。
松下幸之助さんが「企業は人なり」で説いた、どんなに伝統があっても、良い事業内容であってもそれを担うべき適切な人がいないのであれば衰微する、人を求め、人を育て、人を活かすことができれば業績を伸ばし発展していくといわれています。生産性と多様性どちらかを選ぶのではなく、両立する事で変化する環境に適応できる柔軟な働きかたを整えてみませんか。
テレワークに関しまして、何かご不明な点等ありましたら、どうぞテレワーク相談センターまで問い合わせください。
テレワーク相談センター(相談無料)0120-861009(ハローテレワーク)平日9:00~17:00
1回1時間のコンサルティングが3回まで無料

執筆者
一般社団法人テレワーク協会 客員研究員 川田理華子(かわだ りかこ)
(社会保険労務士、ソフトウェア開発技術者<現 応用情報技術者>、交流分析士1級)